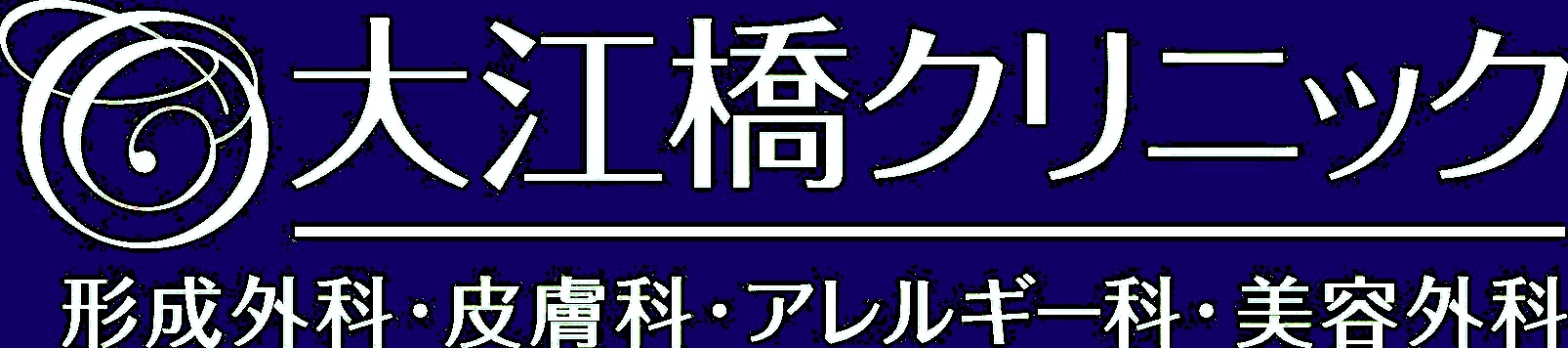会員ページへ
予約専用サイトへ
アレルギー科
〜 Allergology 〜
【 完全予約制 】

大江橋クリニックのアレルギー科は、
皮膚科・アレルギー科専門医の副院長が担当しています。
アレルギーとは免疫の変調です
アレルギー(allergy)とは、ギリシャ語のallos(変じた)とergo(作用・能力)とに由来し、日本語に訳すと、「変じられた能力」あるいは「変作動」という意味になります。
このアレルギーという言葉は、1906年のClemens Freiher von Pirquetの論文のなかで初めて用いられています。
アレルギー、アトピー、アナフィラキシー、という言葉は、その後の研究や実験により命名され、用いられるようになりました。
現在の研究からこれらの言葉は、以下のように考えられています。
アレルギー(広義)とは
免疫反応に基づく、生体に対する全身的または局所的な障害を言います。
”広義のアレルギー”は、
- 血中抗体による液性免疫反応に基づくアレルギーと
- 感作リンパ球による細胞性免疫反応に基づくアレルギー
の2つに大別されます。
アトピー
アトピーは、厳密には液性免疫反応に基づくアレルギーのうちのⅠ型アレルギーすなわちIgE関与のアレルギーを指しますが、 ”狭義のアレルギー”と同意語として使用する場合もあります。
アナフィラキシー
アナフィラキシーはⅠ型アレルギーに属し、全身の各標的器官でアレルギー反応を起こして全身症状の発現をみるものと考えられています。
アレルゲン(抗原)
アレルギーの原因物質は無数にあります
アレルゲンは、私たちの生活環境に存在する物質の中で、主にIgE抗体によって伝達される即時型アレルギー疾患を誘発する物質のことです。
その種類は無数にありますが、日常において比較的問題となりやすい頻度の高いアレルゲンは100種ほどとされて、そのほとんどが空中飛散アレルゲンだとされています。
吸入アレルゲン
ダニ、室内埃(ハウスダスト、ほこり)はアレルギー疾患の原因として最も注目されているアレルゲンです。
その中で一番の原因とされているのが、ヒョウヒダニ(表皮ダニ)です。
総ダニ数の約60〜80%をこのヒョウヒダニが占めるとされています。
ダニは気温25℃前後の暗所で湿度の高い環境下で繁殖しやすいというデータがあり、本邦は比較的ダニが繁殖しやすい環境であると言えるでしょう。
室内に蓄積されるダニのアレルゲン量は、8月〜9月にかけて最大となり、それ以降は徐々に減少して3月〜4月頃に最も少なくなるとされています。
花粉
花粉症の原因アレルゲンである花粉の形状は様々なものがありますが、平均径は約20〜50μmの範囲に含まれるため、ほとんどが上気道粘膜面に捕捉され下気道にまで至るものは少ないとされています。
よって、眼結膜のかゆみ、くしゃみ、鼻水、鼻閉塞感など鼻アレルギー症状や眼症状が生じることが多く、むしろ喘息の起因アレルゲンとなることは少ないとされています。
一番よく知られているのはスギ花粉でしょう。
ですが、イネ科、雑草科の花粉に高い反応を持つ方も多く、スギ花粉の時期が終わっても注意が必要です。
また、花粉アレルゲンは、花粉単独でも抗原性を有する上、大気中のディーゼルエンジン排気ガス中微粒子(DEP)と結合するとアジュバント効果を発揮し、易感作性を獲得することが報告されています。
その他のアレルゲンとして、真菌や食物などが知られています。
アレルギー疾患の多様性
アレルギーの4型:〜型アレルギーとは何でしょう
アレルギー反応は免疫反応による組織障害のタイプで分けられた分類法が多く使われています。
- Ⅰ型アレルギー
- アナフィラキシーショック、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、気管支喘息、蕁麻疹など
- Ⅱ型アレルギー
- 薬剤性溶血性貧血など
- Ⅲ型アレルギー
- SLEなど
- Ⅳ型アレルギー
- 接触皮膚炎など
アレルギー疾患は多岐にわたります
大江橋クリニックでは、アレルギー疾患のうちで主に皮膚症状が中心となるものを診療しています。皮膚科領域のアレルギー関連疾患には、
アトピー性皮膚炎の一部
蕁麻疹の一部
接触皮膚炎・かぶれ
ラテックス(ゴム)アレルギー
OAS(食物アレルギーoral allergy syndrome)
薬物アレルギー、薬疹
昆虫の毒素などによるアレルギー
皮膚血管炎
などがあります。また、
など、耳鼻科や眼科領域のアレルギーの一部も診療を行なっています。
気管支ぜんそくなど、小児科や呼吸器内科、その他の診療科が得意とする疾患は、各専門機関の受診をお勧めしています。