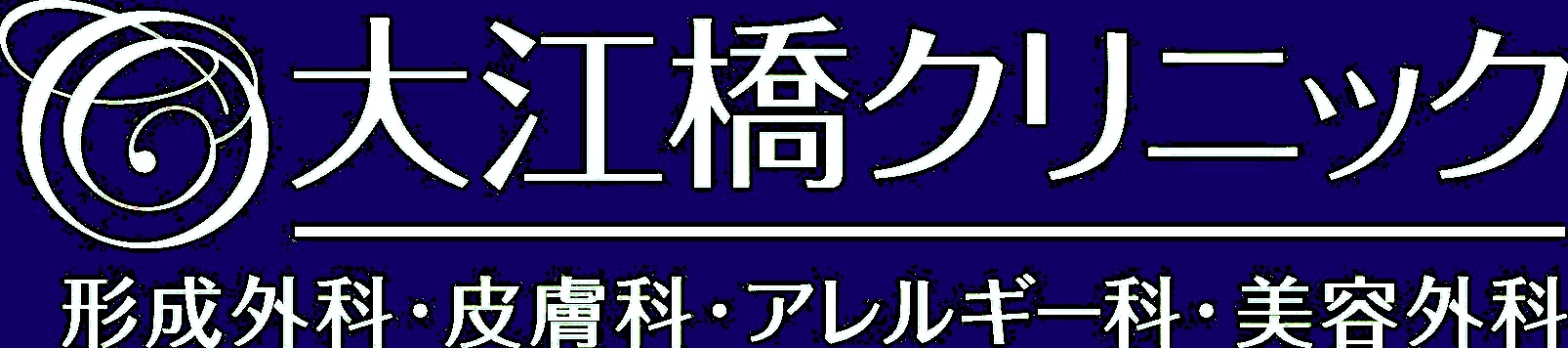インフォームド・コンセント
患者さんが知りたいこと
漠然とした不安を言葉にするのは難しい
医師にとっては毎日のように行っている通常の仕事の一つですが、患者さんにとっては一生に一回しかないイベントであるかもしれません。様々なイレギュラーな状況を日々知恵を絞って切り抜けてきている医師と、書物やネット情報、伝聞くらいでしか知識が得られない患者さんとが同じ土俵に上がるのは元々難しいことです。
医師が様々な経験を積み日々技術の向上に向けて努力していることを理解してもらい、信頼関係を築くことが最も大切です。
その上で経験上最も多く受ける質問のいくつかにあらかじめお答えしてから、情報提供を始めます。
手術に伴う痛み
痛いですか?と聞かれることがあります。手術である以上、全治療期間を通して全くの無痛ということはあり得ないのですが、局所麻酔での手術を受けたことがなく具体的なイメージがない患者さんに対しては場面を分けて説明します。
痛い(かもしれない)場面を順を追って見ていきます。
(1) 手術前:血液検査の時注射針を刺します。その他の検査には痛みを伴うものはありません。ご安心ください。
(2) 手術中:麻酔の注射は目尻から始めます。針を刺す痛み、麻酔薬の注入時に爪でつねられるような痛みがあります。目頭に向けてすでに麻酔の効いたところから注入を追加します。このとき針を刺す痛みはありませんが、麻酔薬の刺激による痛みはあります。麻酔は注射直後から効くので、注射した部位はすぐ無痛になりますが、触ったり押したりしている感覚はわかります。
麻酔が効いている間は原則的に患部の痛みはありません。筋肉を触っているときに目の奥を引っ張られているような鈍い痛みを感じることがありますが、一過性でそれほど辛いのもではありません。
(3) 手術終了間際:お酒が非常に強い人などは麻酔薬の分解も早いため、切れてくるのが早い傾向にあります。また手術部位の状態が悪い場合(再手術で瘢痕が多い、皮膚炎がある、血圧が高い、非常に緊張して心拍数が多い)などでは出血が通常より多いため、それに伴って麻酔薬が組織から洗い流されたり神経の過敏性が高まったりして、予想より早く麻酔が切れてくる場合があります。
こうした場合は痛いと思われる位置に麻酔注射を少量追加します。注射の痛みはありますが、手術操作に伴う痛みはなくなります。
(4) 手術終了直後:麻酔が効いていれば無痛のまま終了できますが、切れかけてくると怪我をした後のような痛みが徐々に復活してきます。痛み止めを内服するとほとんどの場合治ります。
大江橋クリニックでは通常は終了直後、場合により手術開始前に痛み止めの錠剤を飲んでいただくことで、痛みの増強を防止しています。
(5) 術後から翌日にかけて:痛み止めを内服していただくと、ほとんどの場合ほぼ痛みなくお過ごしいただけます。通常の経過であれば翌日には全く無痛とおっしゃる方が多いです。ガーゼ交換などで患部に触れると多少痛みを感じることがあります。
例外的に、患部の状態が悪いなどで術後も出血が続いたり、何かのトラブルで一旦止血していた部分が再出血した場合はズキズキとした(拍動性の)痛みを感じることがあります。こうした場合、通常であればガーゼ等で圧迫を続けることで血は止まりますが、出血が続き腫れが増大してきた場合などは緊急に患部の傷を開いて止血操作が必要になります。大江橋クリニックでは過去に1回だけこうした再手術を行った経験があります。
術後すぐの飲酒や、激しい運動、患部を何かにぶつけた、お渡しする止血剤を内服しなかった、などの原因で再出血する可能性があります。
(6) 抜糸時:糸を抜くのに麻酔は必要ありませんが、ハサミの角が当たったりピンセットで糸を引っ張るときにチクチクした痛みがあるかもしれません。
体質により、腫れて糸が皮膚に食い込んでいたり、結び目の糸玉や糸の途中が皮下に埋もれてしまったり、滲出液があって糸が皮膚にくっついていたりすると、糸を引っ張るときの痛みを感じやすいようです。目頭の結び目を切るときにちくっと痛いことがあります。しかし糸を抜いた後は引っ張られる感じがなくなり楽に瞼が開きます。
(7) 長期的な痛み:通常の経過では術後に患部が痛むことはありませんが、目の奥が重い、違和感がある、鈍い痛みがあるなどと訴える患者さんもあります。ほとんどの場合耐え難いものではなく、なんとなく気になるようなレベルですが、非常に長い間(数年間といったレベルで)消失しないこともあります。
外観の変化
手術をすると見た目が激変しませんか、はでな二重瞼になって人相が変わりませんか、びっくりするような不自然な顔になりませんか、などと聞かれることがあります。
芸能人の例や、インターネットに流れるいわゆる失敗写真などを見て心配になるようです。
もちろん見た目の変化はありますし、むしろそれを目的として行う手術です。なんらかのトラブルがあったとしても「異様な見た目」になることは稀です。しかし稀ではあっても術前の患部の条件によっては、美容的に満足できない結果になることもあり得ます。(もちろんその際には原因を考えた上で修正手術を計画します。)
ある程度の年齢で発症した多くの方に共通する症状である「眉が上がってひたいに皺がより、眉と目の間が離れた状態」は、手術が成功すると劇的に改善します。大江橋クリニックでは「若い頃(10代の頃)のイメージに戻る感じです」と説明しています。別人の目と取り替えるわけではなく、あくまでご自身の目の印象が下垂する前に戻るだけなので、自分のままで若返った感じになります。
術前一重瞼であったり目が落ち窪んでいたりした場合などは、術後すぐのややはっきりとした二重瞼にすぐには馴染めないこともあります。しかし大抵の場合は2週間ぐらいして腫れが落ち着いてくると、術後の方が自然な感じがして好ましく思われ、以前の顔を忘れていきます。
しかし一部の患者さんでは、左右差が生じて不自然に思われたり、瞼の一部(主に内側、目頭の近く)がうまく持ち上がらなかったり、まつ毛際の腫れが非常に長引いたりすることがあります。十分な結果が出せなかった場合は、半年から1年程度経過を見て、その間に改善が見られなければ再手術を行います。
ダウンタイム
ダウンタイムはどのくらいですか、何日会社を休めばいいですか、バレませんか、という質問もよくありますが、これはお答えしにくい質問です。
瞼の腫れや皮下出血などの範囲は非常に個人差が大きいので、確実なことは言えないのですが、それ以上にどの程度の状態なら他人に(会社の人に、家族に、すれ違う他人に)変に思われないか、という基準も個人差が大きいのです。
翌日は流石に瞼の上にガーゼが当たっていますので、誰が見ても手術を受けたことがわかりますが、3日目ぐらいには(糸がついたまま)仕事に行ってもバレませんでしたと報告してくれる人もいます。男性は比較的皮膚が厚く皮下出血が目立ちにくいので、抜糸してその日から出勤しても問題ないケースが多いようです。
皮下出血が生じた場合、2週間くらいは黄色い色が残りますので、いわゆるダウンタイムの目安としてはそれぐらいかと思いますが、メガネをかけていればそれ以前でもあまり目立たないものです。印象の変化に関しては、メガネのフレームを少し濃い色の太いものに変えたり髪型(特に前髪)を変えたりすると気づかれないことが多いようです。
一部非常に外見が気になるタイプの患者さんがいるのも事実で、4ヶ月以上、中には半年たっても外出できない、知人に会えないとおっしゃる方もいます。これは結果の良し悪しには関係なく、変化したこと自体が受け入れられないのだと思います。手術を受けたことが罪悪感につながっているような方もあります。
人間としてあり得ないような目にされた、こんな目の形の人は他にいない、誰が見ても変だと思うはず、買い物にも行けない、と訴えて来られる方もありますが、全く自然ですよ、普通ですよと申し上げてもまず納得してはいただけません。
失敗したらどうなる
一般論として、切開するラインは美容的な効果を狙った小細工はせず、ご本人の生まれ持った目の形を生かす自然なラインを探してデザインします。このため想定外の形になることは少ないと思います。失敗の定義にもよりますが、前項の最後のようなケースは別として結果に満足できない場合は概ね以下のように分類されます。
(1) 左右差:片方のみの手術、あるいは左右別々の時期の手術の際に生じやすく、原因は多くの場合筋肉の収縮力の左右差にあり、先天性であることに気が付かなかったためであることが多いです。両側同時の場合は筋肉量などに左右差があっても手術中に調整できるため比較的生じにくいです。多少の左右差は時間の経過とともに周囲の表情筋の協調作用によって改善することがあります。改善しない場合は半年以上空けて腫れが治ってから再手術します。
(2) 低矯正:手術中は十分と思われたのに、術後腫れが引いてくるとぱっちり開かないケースです。術前に長いこと目を開けるとき力を入れて見開いている時期が続くと、それが習慣になっていて手術中の確認の時にも思い切り目を見開いてしまうこと、などが考えられます。開きすぎたと思って少し調整して元に戻し、結果的に前転量が不足していた、というケースが多いように思います。手術中の確認をあまりしなくなってから、このケースは少なくなりました。
(3) 過矯正:手術中に何度確認してもあまり開かなかったのに、術後に開きすぎて違和感が生じるケースです。麻酔で筋肉が麻痺するわけではなさそうです。緊張しすぎてうまく開瞼できなかったり、手術室内が眩しくて開けられなかったり、片方だけ開けようとしてできなかったりすることも考えられます。
開けすぎて閉じなくなると角膜障害など実害が生じるので、疑わしい時は控えめにして手術を終えます。過矯正が生じた時は眼輪筋の強化トレーニングなどで閉じる力を増やすよう指導していきますが、改善しない場合再手術します。再手術では前転量を減らすというより、前回手術の瘢痕をきれいに取って縫い直すだけでよくなることが多く、手術中に何度も縫い直して確認したことによる術後の出血や腫れで瞼の内部で癒着が生じてスムーズに閉じなくなるのが原因のように思います。
(4) 三角目などの形の異常:他院術後の再手術などの場合、眼瞼挙筋の内外角を切断してあったり靭帯を切除してあったりして瞼のカーブがうまく作れないことがあります。眼瞼挙筋腱膜の内側(目頭側)は非常に薄く、脂肪化していたり穴が空いていたりして瞼板に固定できないことがあり、そのため内側が下がってしまうことがあります。もちろん腱膜全体をやや内側に移動させたり、瞼板への縫合位置を工夫したりするのですが瞼板自体内側が欠損していたり非常に脆かったりすることもあります。また出血しやすい場所であるため術後の出血などで固定が外れてしまうこともあると思われます。
生じた場合はうまく治す方法がなく、時期を待っての再手術に期待するしかありません。体質や瘢痕の性質等によっては再手術を行なっても同じ形に再発することもあります。
(5) 眼瞼痙攣の発症:形は良くなったのに目を開けるのがつらい、眉間に皺がよる、眉に力が入る、などの症状が術後に出てくる方がいます。
眼瞼痙攣の影響もあって開きにくかったのに、見落としていたケースです。術前に気がついた場合は神経内科等をご紹介してまず眼瞼痙攣の治療を開始するのですが、眉の動きをあまり注目していなかった経験の浅い頃に時折術後に気づくことがありました。眼瞼痙攣の治療がうまく行って、下垂症状が残れば後から手術してうまくいくケースはあります。
(6) 肥厚性瘢痕:瞼には肥厚性瘢痕は生じないというのが教科書的な定説ですが、実は結構多いと感じています。表面に見えないためないことになっていると思います。瘢痕は瞼の内部の腱膜を縫合したあたりから生じます。ケロイドと違い長期的には柔らかくなって消失するようですが、長期間違和感に悩まされることがあります。アレルギー体質に伴い手術に使用したナイロン糸などを核として生じたものは再手術して切除した方が良いかもしれません。
(7) いわゆる「ハム」状態:瞼の縁が腫れ上がって太くなり、長期間引かないものです。実態は肥厚性瘢痕であると思います。縁の眼輪筋を切除する際の出血や術後の圧迫不足などで生じるように思います。真皮の厚さや縫合の仕方によっても想定以上に腫れることがあります。頻度はそれほど多くありませんが、発生すると改善するのに時間を要します。
手術法の説明
通常は「眼瞼挙筋前転法」で行います
診察の際に病状の現状と治療法を説明していますので、眼瞼下垂症の治療の中核は、瞼を持ち上げる機能が弱まっている「上眼瞼挙筋」を適切な位置に固定し直して、意識的または無意識に目を開けようとした時に上眼瞼が最適な位置に挙上するよう調整する手術操作が中心となることは、既にご理解いただけているものと思います。「眼瞼挙筋前転法」で手術を受けること自体の同意は得られているものとします。
手術の詳細
切開の位置
上眼瞼挙筋にアプローチするには結膜(瞼の裏側)を切開する場合と、皮膚側(瞼の表側)から切開する場合があります。大江橋クリニックでは全例、皮膚側の重瞼ラインを切開します。したがって必ず重瞼ラインにわずかな傷跡(瘢痕)が残ります。また眉側の皮膚が特別に分厚い場合、腫れが落ち着くまでの間二重の幅や形状がやや不自然に見えることがあります。
目立ちにくい場所ですが「傷跡が目立つ」かどうかは術後経過とご本人の体質が影響し、主観的にはご本人の性格とこだわりにもよたるめ、「一般的には」気になるような傷跡が残る場合は少ない、と申し上げることしかできません。
これ以外の方法(眉下切開、埋没法、腱膜やゴアテックス等によるつり上げ術、結膜側からのミュラー筋タッキング、小切開法等)は行いません。その理由はそれぞれの項目のところで説明していますが、基本的には術者に経験が少なく患者さんの満足が得られる自信がないと申し上げておきます。
皮膚切除
切開に伴い皮膚の一部を切除します。ほぼ全例に多かれ少なかれ眼瞼皮膚のたるみがあり、これを適切に切除しないと自然な形に仕上げることができないと考えています。たるみが大きい場合は目尻側切開を長く延長します。
皮膚の延長が強い場合は一度で全て切除すると綺麗なカーブが作れなかったりご本人の術前イメージとかけ離れた仕上がりになる危険もあるため、切除幅は概ね1センチを超えないようにしています。
奥二重のイメージを変えたくないなどやや特殊なご希望通りに仕上げるためには、切開位置を適宜工夫しますが、皮膚の性状により思い通りの結果が得られない可能性もあります。
筋膜の固定と皮膚縫合
上眼瞼挙筋の筋膜は適度に前転して瞼板に3箇所ナイロン糸で縫合固定します。皮膚縫合は通常目頭から目尻方向に連続縫合で行います。皮膚の緊張の程度などによっては、目尻側に結節縫合をいくつか追加する可能性があります。
手術終了時には瞼の形に合わせたガーゼを切って重ねて当て、茶色のサージカルテープで厳重に固定します。このテープは翌日まで外せません。このため上方視野は制限されますが、下の方は見えるので歩いて(もちろん交通機関を利用して)帰ることができます。翌日受診するまで触らずそのままにしておいてください。冷やしたり消毒したりする必要はありません。出来るだけ何もせず、静かにお過ごしいただきます。
合併症とリスクの説明
合併症とは
合併症とは手術に伴って起きる、想定外の不都合な症状の総称です。
手術はもちろん常に100点満点を目指して行うわけですが、様々な理由で術者の思い通りの結果が出なかったり、様々な不愉快な症状や医学的に好ましくない状態が出現することがあり、手術に合併して発生することから「合併症」と総称されます。
手術に過大な期待を抱かないこと
眼瞼下垂症手術は繊細で難しい手術だといえ、特に美容面での出来上がりは芸術作品のような側面があります。術者の技量が関係することはもちろんですが、体調や術前術後の過ごし方などの影響もあり、常に完璧な仕上がりを保証することができません。実技テストや体操の試技のようなものでほぼノーミスであっても100点満点はなかなか取れないものなのです。
大江橋クリニックでは患者さんに今回の手術に何点つけますかとお尋ねすることがあります。お世辞も含め100点満点ですとおっしゃって頂いたことは実は数えるほどであり、90点、85点、くらいいただけるとかなり嬉しく感じます。手術とはそうしたものであることをまずご理解ください。
短期的な合併症
手術後にまず確実に起こることは、皮下出血(内出血)と腫れです。皮膚切開、組織の剥離や切除、高周波や熱などによる止血、糸による縫合を行うので、細胞は壊れ、細い血管やリンパ管は切れてしまいます。怪我をした時と同じです。すると漏れ出した組織液や血液、壊れた細胞などから体調の異変を知らせる細胞間伝達物質が大量に放出され、それに反応して様々な炎症細胞が患部に集まってきます。
通常であれば微小な出血は手術の終了後も24時間程度は続き、腫れは翌日以降にピークを迎えます。体質により瞼の腫れは数ヶ月から数年続くこともあります。(ただし人目に付くようなはっきりとした腫れは数日で治ってくることが多いようです。)皮下出血はパッと見てわかる色の変化としては通常2週間程度続き、その後はほぼわからなくなります。大江橋クリニックの平均的な術後経過としては、翌日に上眼瞼のふち(切開線と睫毛の間)が赤くなります。再手術など条件が悪い場合は目尻や目頭にも皮下出血が拡大し、下眼瞼に紫斑(内出血斑)が拡大することがあります。
兎眼と呼ばれる「目が閉じない」状態は、腱膜を前転した場合は必発で避けることができません。これに伴って目が乾くドライアイ症状も起こります。
通常の経過であれば1週間から1ヶ月程度で意識的には閉じられるようになります(寝ている時や無意識には開いている場合がある)。角膜障害が起きるほど重症にはならないのが普通で、通常はドライアイに対してしばらく眼軟膏や目薬をお使いいただくことで対処します。
術後に麻酔が切れても痛みが出ることは通常ありません。出血が多い場合は当日少し痛みを感じる方も稀にいます。
ごく稀に起こる事故
通常の経過であれば翌日には洗顔できるようになりますが、患部を覆っていたガーゼが外れるのに伴い、ナイロン糸が切れたり傷が裂けて出血する方があります。大事に至らない方がほとんどですが、緊急に再縫合を行った例があります。
長期的な合併症
先天性の場合など筋肉の動きが元々悪い場合は、上方視や下方視の際に左右差が生じることがあり、これは完全には治すことができないので、視線に伴って頭を同時に上げ下げする練習などを行なってカバーする必要があります。眼輪筋のトレーニングやウィンクの練習である程度改善することができます。
腫れが引いても正面視で左右差が残ったり、低矯正(開瞼不足)、過矯正(開きすぎ)になってしまうことがあります。ある程度待って改善しない場合は、いずれ時期を見て再手術を行うことになります。(再手術に関しては通常もう一度手術料等一連の費用がかかります。)
一般的な経過説明
コンタクトレンズを使用されている方
つけ外しのために瞼を触る必要がある方は、通常抜糸後もう一回(通常は術後2週間目くらいに)診察し、問題がなければ許可を出します。
ソフトコンタクトレンズを使用されていて、瞼に手を触れずにつけ外しできる方はご相談の上もう少し早い時期から許可することもあります。
目が完全に閉じない間
術後は目を開けるのは楽になりますが、逆に目を閉じるのが難しくなり、完全に閉じられるようになるまで時間がかかります。
完全に閉じられないとドライアイ症状が出やすいので、乾燥防止のための目薬や眼軟膏をお使いいただくことがあります。
また眼輪筋など周辺の表情筋のバランスが変わるので、抜糸後にウインクなどの練習をしてもらい、早く腫れが引いて閉じられるように援助することがあります。
レーザーによる美容治療を続けている患者さんには抜糸後すぐから再開していただくことで、早く脹れを引かせることができます。
しばらくは二重の幅が広くなります
術後は特に瞼の縁が腫れるので、二重の幅がとても広く感じられます。最終的には大抵の場合おとなしい細めの二重に落ち着きますのでご安心ください。
眉の下の窪みや下眼瞼の膨らみは改善してきますが、個人差があり落ち着くまで時間がかかります。
目頭の二重の始まりの位置は、その人なりの自然な位置に落ち着きます。ただし腫れの引き方によっては左右差が生じることがあります。
術後1ヶ月程度にかけて傷跡が固くなる時期があり、目頭に斜めの線が出たりすることがありますが、傷跡の赤みが落ち着く頃になると馴染んできます。
目尻の傷はしばらくは赤くくっきりしていますが、そのうち細いシワのようになり消えていきます。目を開けるのが楽になるにつれ眉が大きく下がる方が多いのですが、一部に想定以上に外側(眉尻側)が大きく下がって弛んでくる方がいます。皮膚切除が不足したと思われる場合は、時期を見てもう少し皮膚を取り足します。
結果が予想に反した時
他院で手術したが結果が良くなかった例

左の患者さんは、右眼の先天性眼瞼下垂症に対してすでに複数の病院(いずれも大阪では著名な形成外科のある病院です)で4回の眼瞼下垂症手術を受けています。
先天性では健側と全く同じようにぱっちり開けようと思うと色々な不具合が出ることもあるので、多少開き加減が少なく左右差があっても我慢しなければならないことがあるのですが、この患者さんは各医療機関でそうした説明を術後十分に受けなかったため、もう少しもう少しと手術を繰り返した末、こうした結果になってしまったようです。確かに瞼は開いてはいるのですが、非常に不自然な外観です。
手術を繰り返したことで、眉の下が大きく陥凹して不自然にくっきりした幅広の二重瞼になっています。この患者さんの場合には、眼瞼下垂そのものは前医の手術で一応治っていますので、形の不自然さを改善する目的で手術をしました。






瞼の中は傷痕の硬い組織で充満しており、眼輪筋などの筋肉も眼窩脂肪も大部分切除され、本格的に改善するには脂肪移植が必要でしたが、そこまでは望まないということで二重のラインを浅くするにとどめることにしました。(癒着した二重のラインを浅くするのは、脂肪移植なしではかなり難しい手術になります。)
基本的には筋肉の処理は行わず、従って下の写真でもわかる様に目の開き方自体にはほぼ変化はありませんが、不自然さはだいぶ改善しました。左側を右に合わせて自然な二重にするとより左右差が目立たないのでしょうが、患者さんが希望されずそのままとしています。
無理して完璧を求めない方が良いこともあります
大江橋クリニックでは、条件の悪い難しい患者さんでも何とか美容的に許容できる結果を得られるよう、時間のかかる困難な手術も行なっています。
結果が予想通り出なかった場合、その原因が医師の拙い技術にあるのか、患者さんの側に隠れたリスクがあったのか判断するのは難しいものですが、拙速に下手な医者に失敗されたと思い込まず原因を探ることが次の手術を成功させる鍵になります。他院で失敗された、と相談においでになる患者さんは多いので、最初のうちは「下手くそな医者もいるものだ」と思い義侠心のようなものを発揮して気軽に再手術を引き受けていました。しかし、次第に失敗には失敗する原因があるのだと感じることが多くなり、少なくとも一度は元のお医者さんに相談するよう勧めるようになりました。
うまくいかなかった理由は、執刀医が一番発見しやすいと思うからです。手術中に何か普段と違う点があったとか、術後にこんなエピソードがあったとかもう一度見直すことで、次はうまくいく可能性が高まります。もちろんそれが自分の技術的水準ではクリアできないと思った場合は、潔く他の医師に紹介すべきだと思いますが。
様々な眼瞼下垂症の初回・修正手術をはじめ、瞼のたるみの改善、瞼のできもの切除など、瞼の形を損なう様々な原因をとりのぞき、瞼をきれいに整える手術を得意としています。
もちろんこういったサイトの常として、症例写真の多くは(リスクや合併症の説明をする場合を除き)結果が良くご本人も納得されている患者さんの写真を使用しています。患者さんによっては残念ながら左右差が残るなどご希望通りに仕上がらないこともあります。骨格や皮膚の状態、前医の手術後の傷の程度などによっては、再手術を行ってもきれいに修正できないことすらあります。
大江橋クリニックでは、たとえ条件が悪くともそれなりの結果が出せるよう、それぞれの患者さんに対して真剣に向き合って治療しています。
大切なご注意
もちろん手術ですからダウンタイムもリスクもそれなりにあり、回復までの時間にも個人差がかなりあります。
また元の症状の違いによって誰でも左右差なく綺麗に治るという保証はありません。特に、眼瞼挙筋の力が生まれつき左右で違う先天性の眼瞼下垂では、一度の手術で左右差を完全に無くすことは難しいものですし、筋肉の動きが悪い場合には「ぱっちりあけてしまう」ことで逆に「目がつぶれない」という症状が悪化してしまうため、ほどほどの改善で我慢しなければならないこともあります。
患者さんの日常生活で何が困るのかを考慮せず、単純に「ぱっちり開くように」手術され、術後のフォローも不十分なため苦しんでいる患者さんも時々見られます。手術後は眼瞼挙筋だけでなく目の周りの多くの筋肉が今までと違う動きをするようになるため、人によっては術後の「筋トレ」が必要になったり、落ち着くまで数ヶ月を必要としたり、視線を動かす時に不自然にならないように練習しなければならないこともあります。
手術とは、そうした術後管理も含めて一つの治療です。手術したらそれで終わりではなく、術前から術後まで長い時間かけて良い結果を得るよう努力することで、初めてその手術が成功したと言えるのです。